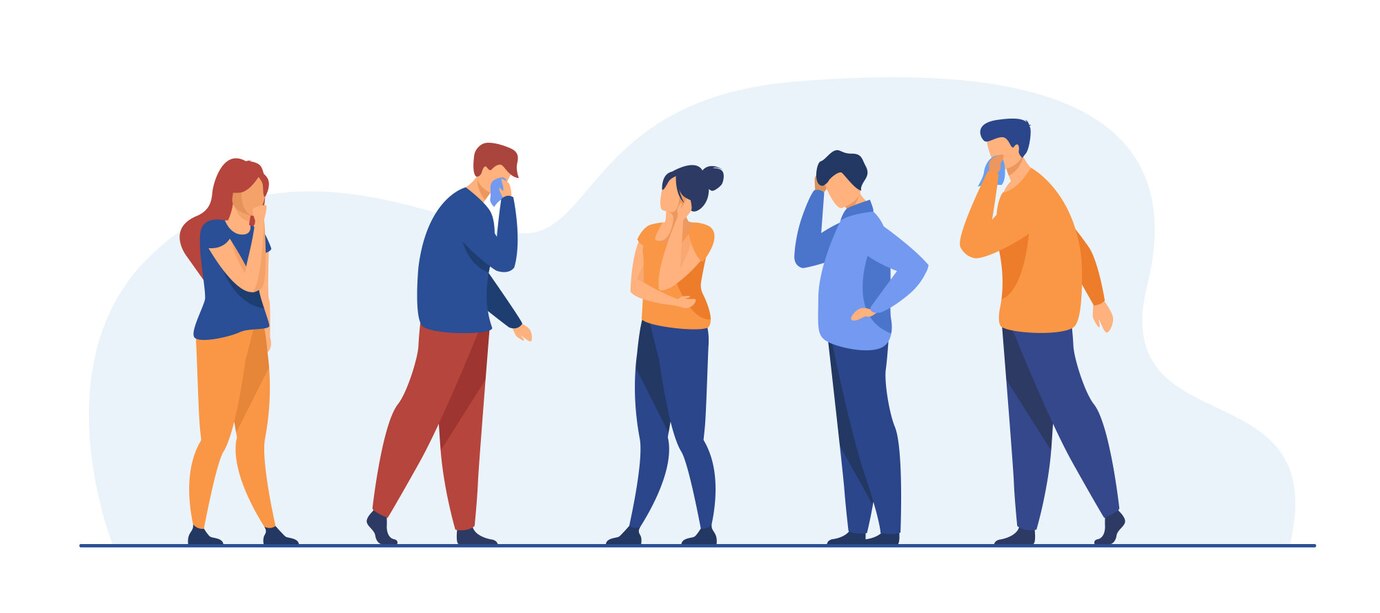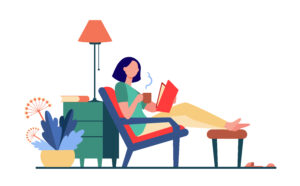悩んでいる人
悩んでいる人看護師一年目の新人だけど、何をやっておけばいいか知りたい。
注意点とか乗り越え方があれば聞きたい。
今回はこんなお悩みにお答えします。
参考までに、私は新卒で1000床超えの大病院に就職して働いていました。
苦しみながら看護師一年目を乗り越えて看護師としてのキャリアを築けたので、今回はその時の方法を少しでもお伝えできたらと思います。
苦しくて辛い学生時代、実習、そして国家試験を乗り越えて念願の看護師になった皆様に、微力ながら参考になれればと思っています!
今回は、看護師一年目の時に①勉強していてよかったこと ②勉強しておけばよかったこと ③気になるアレコレの一問一答 を中心にお伝えしたいと思います。
それでは早速次章からご紹介していきます。
看護師一年目(やってよかったこと)
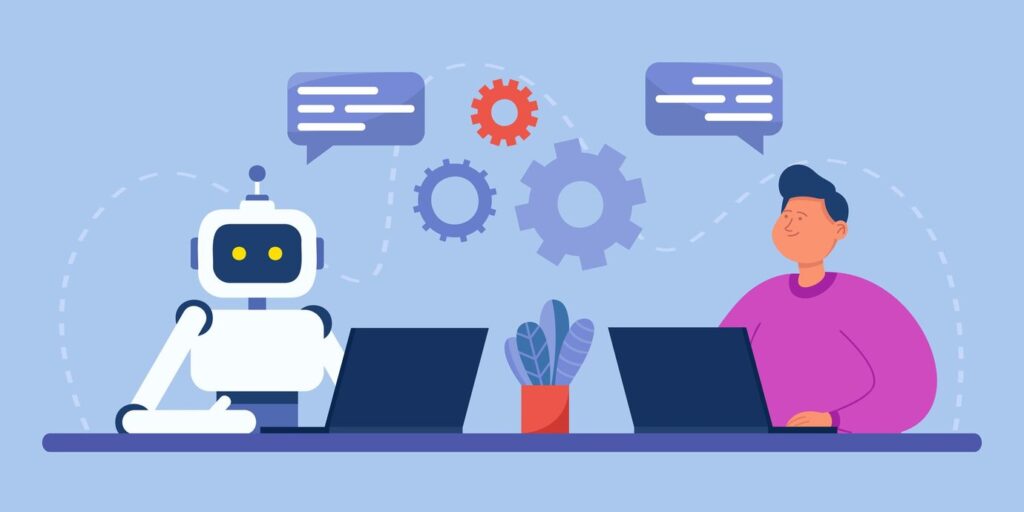
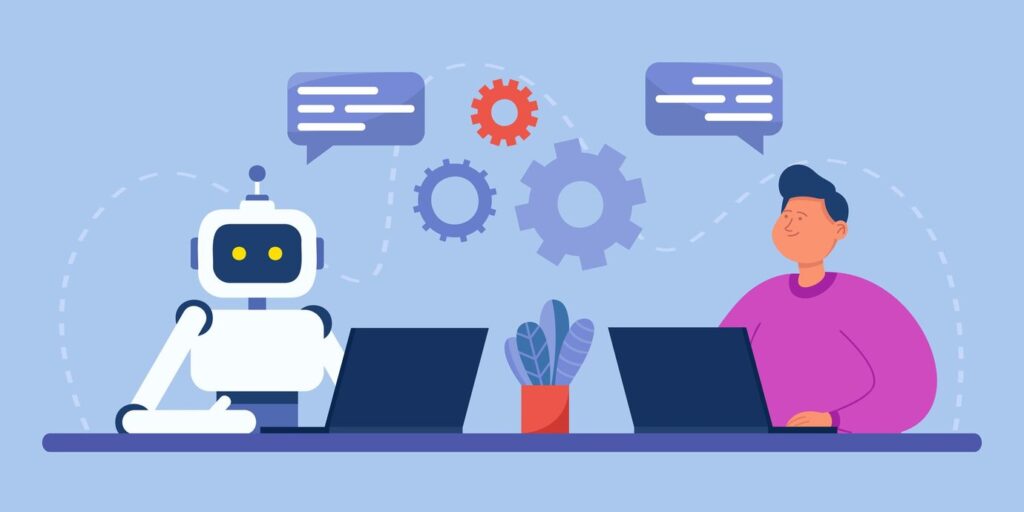
ここでは、看護師一年目時代にやっていてよかった事をご紹介したいと思います。
ぜひ参考にできそうな部分は取り入れてみてください!
入職前
・国試の内容を忘れない
国試でバイタルサインや採血データの正常値、解剖的な知識を一通り学ぶと思いますが、入職後もある程度覚えたままだと勉強の下地があるので便利でした。
特にバイタルなどの正常値はほぼ毎日確認されるので、しっかり覚えておくことをおすすめします。



私は入職日に配属部署が発表になったのですが、もし事前に分かっていたらその領域の解剖生理やよく使う薬剤の復習をする事をおすすめします!
・たくさん遊んでおく
看護師生活が始まると、しばらく帰って勉強して寝て、週末は体力を回復しての毎日です。
おそらく最初のうちは暦通りの出勤が多いと思うので、まずは春休みのうちに旅行に行ったり友達と遊んだりしておく事をおすすめします!



特に海外旅行は行けたら学生のうちに行くべきだと思います。
・ストレス発散の趣味を見つけておく
どの仕事も楽な仕事はありませんが、看護師もそうです。
しんどい生活の中でリフレッシュに助けられた機会は何度もあります。
そのため、なるべく早く自分が好きなこと、ストレスを解消できる手段をたくさん見つけておいてください!
もし趣味がネットサーフィンしかないと言う方は、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。


入職後
・同期と親睦を深める
これから苦楽を共にする同期は、最初は数少ない仲間になります。
一緒に勉強したり、休みの日に食事に行ったり、しんどかった日に愚痴を言い合ったり、、そうやって乗り越えてきました。
仲良くしておいて損はないので、積極的にコミュニケーションを取っておくことをおすすめします。



私は同じ部署に同期が4人いましたが、もし同期がいない人は年齢の近い先輩などと仲良くしておくと、病棟でも過ごしやすくなると思います!
・検査値の正常を覚える
部署によって診る疾患は全く異なるので、行う検査はもちろん全く違います。(共通するものもありますが)
眼科なら眼圧の正常値、脳外科なら神経症状、救急ならAガスの値など色々あります。
まずは自分の部署で基本的に行われている検査と、その正常値を覚える事が大切です。



正常が分かっていないと異常もわからないので、まずは正常値を頭に叩き込みました。
・物品の場所を覚える
新人看護師にできる事は最初はほとんどないです。
私はまずシャドーイングをしつつ、徐々に先輩に変わってバイタルサインを測定したり、記録をやったりと育ててもらいました。
もちろんイレギュラーや急変が起きた時には戦力になれません。
そんな時にできるのが、物の場所を覚えて先輩たちの足になる事です。
分かりやすく貢献できますし、後々自分で全て物品の準備が必要になった際にも役立つので、意識的に物の位置を覚える事をおすすめします!
・略語を覚える
先輩たちは必ず略語を使っていると思います。
何となーく覚えるのでなく、ちゃんと自分も使えるようにしらべておく事をオススメします!
最初は訳が分からないですが慣れます。



アッペ、ギネ、ウロ、カテ、グラ、マンマ、ツッカー
(調べてみてください笑)
・解剖を復習する
看護師はCTやMRIなどの検査結果をみて、診断はしませんがアセスメントに活用する事が求められます。
そんな時に、例えば脳の構造を理解しておけば、CTなどの画像も何となく理解できますし、医師との会話に活かせたりとメリットが大きいのでおすすめです。
ただ、解剖や画像データを机で学んでも、実際見たら全然違う!わからない!という事は多々あるので、日々の患者さんのデータをみて振り返りながら成長していくのが1番大切だと思います。



私は個人的にCTとMRIの結果を見るのに苦労しました。
ただ、毎日触れることで少しずつ理解できました!
看護師1年目(勉強しておけばよかったこと)
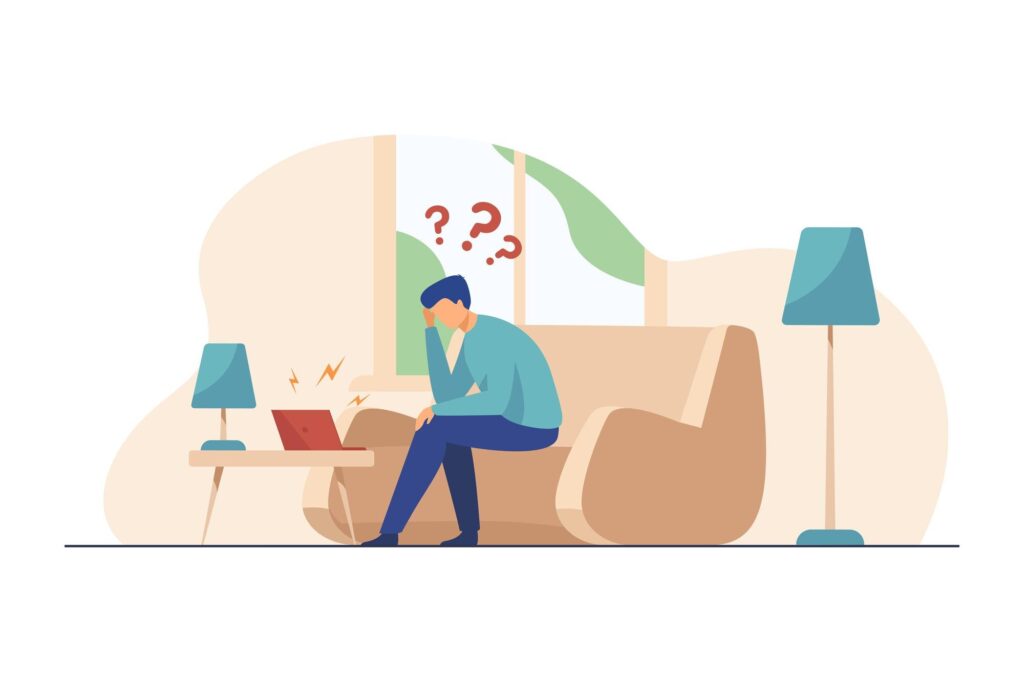
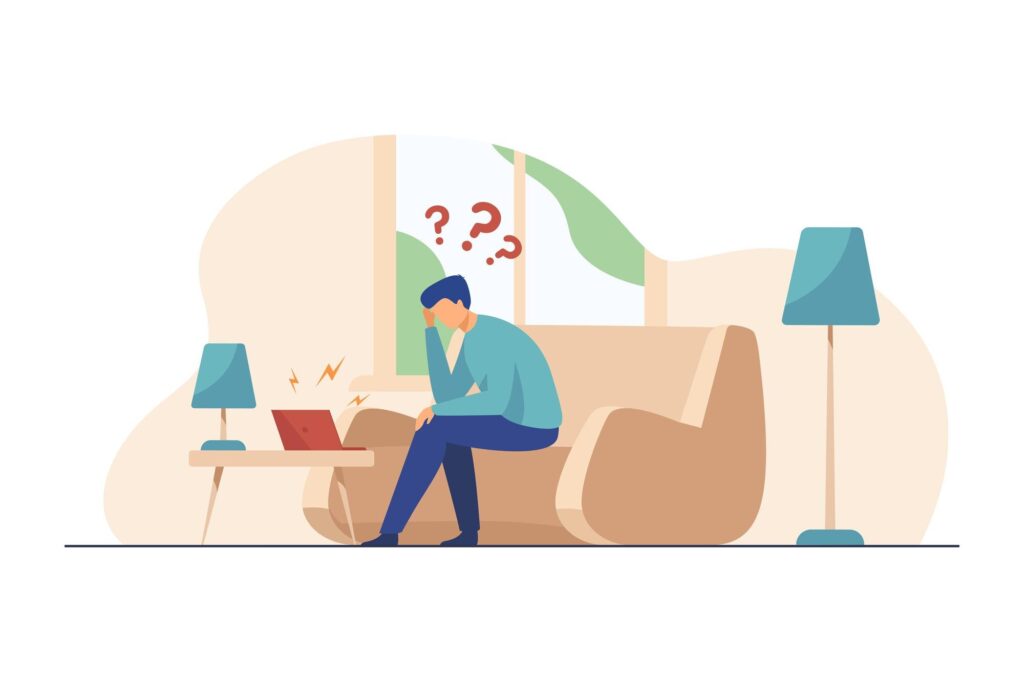
ここからはやっておけば良かった項目になります。
ぜひ参考にして頂いて、皆様は取り組む事をオススメします。
急変対応
病院である以上、何かしらの疾患を抱えた人である事は間違い無いです。
急変はいつ起こるか分からないので、その時がきたら対応できるようにしっかりと備えておくことが大切です。
研修でやるテンプレの流れを覚えるだけでなく、アセスメントの方法や、自分がその時にできる役割などしっかり覚えておくと、いざとなったときに動けるのでしっかり形にしてみてください。



まず急変時のアセスメントABCDEを知る、そして症状別の対策(けいれん、CPA等)を一つずつ潰していけるといいです!
全身管理の意識
これは正直すぐに理解するのは難しかったのですが、とても大切になります。
眼科なら目、脳外科なら脳をまず理解しますが、もちろん人間の体は1つの臓器だけで動いていません。
眼科なのに血糖値が高いと手術は止めていましたし、脳外科なのに呼吸状態が悪化するなど、最初はよく関連が分かっていませんでした。
ただそれらがどう関連しているか、また医師は何を目的にこの方針で治療しているかを確認していく事で、全体を理解していくことが徐々にできるようになります。
アセスメントの幅を広げる
一つの症状の原因は複数ある事が多いです。
ただ起きたことに対して淡々と物事をこなすだけだと、看護ではなく作業になってしまいます。
忙しいとそうなりがちですが、少しずつアセスメントの幅、知識を増やしていくことで良い看護師になっていけるので、日々の積み重ねを忘れないことが大切です!



慣れてくると特に中だるみして楽な方法で、淡々と仕事するようになってしまっていました。時々、ただの作業になっていないか自分に問いかけてみてください。
看護師1年目(気になるアレコレ)
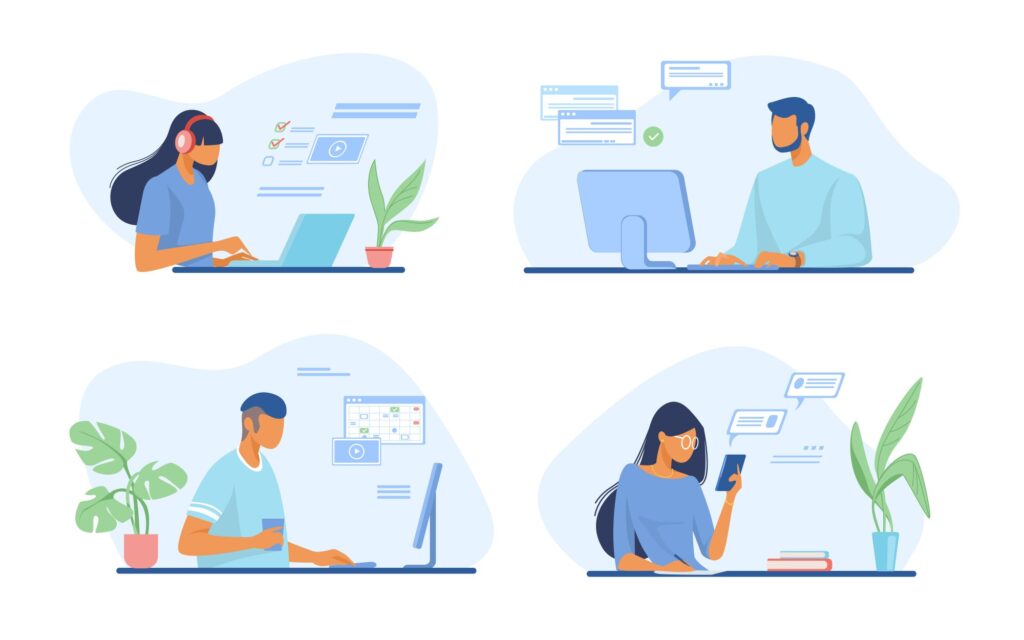
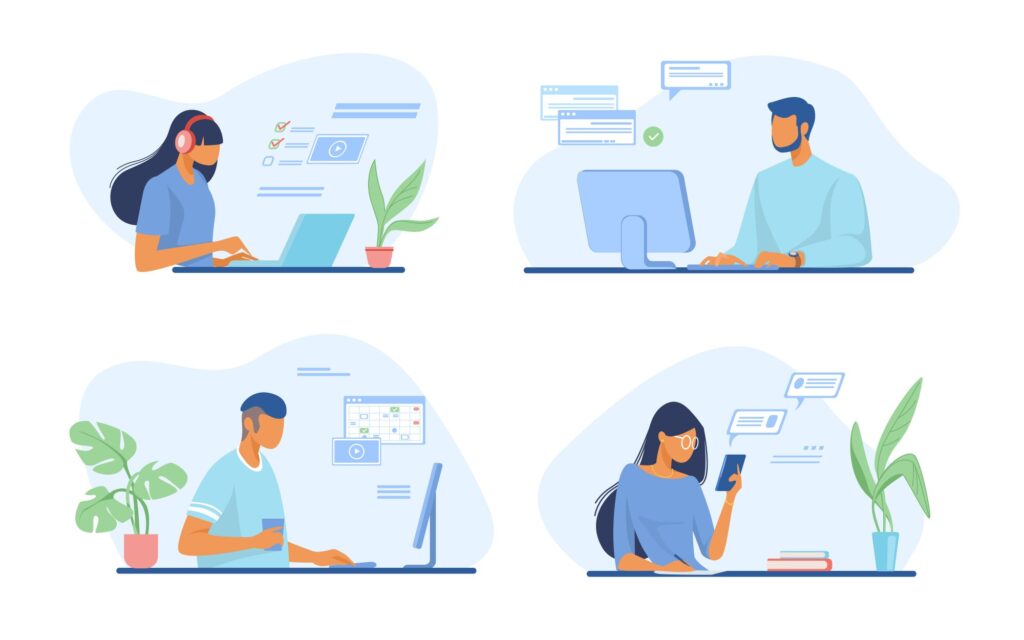
ここに写真🤩
ここからは、新卒看護師の色々な疑問や、自分が入職前に抱いていた疑問・不安について一問一答でお伝えしたいと思います。
もちろん人や入る病院、病棟によって色々違いはあると思うので、あくまで私の個人的な感想にはなりますが、できる限り細かく書いていきます。
夜勤は慣れるか?
結論、慣れます。
最初は夜勤までどう過ごしたらいいか分からず、生活リズムを作るのが難しいですが、徐々に朝は何時に起きて〜や昼は何時まで寝て〜という自分なりのリズムがついてくるので大丈夫です。
(もちろん夜は眠いししんどいので、カフェイン入れたり明けで自分にご褒美をあげたりして乗り越えてました)



私は20時30分〜9時までの夜勤だったので、早起き→昼から夕方まで昼寝→18時頃に起きてご飯と準備という流れで過ごしていました!
お局はいるか
います。
どこの部署にも大抵1人はいます。
理不尽なことを言ってきたり機嫌に左右されている生き物なので、自分がそうならないように反面教師にして生きていました。
幽霊は出るか
私は見たことありません。
霊感が無いので見えなかっただけかもしれませんが、おやっ?と思ったこともなかったです。



霊感のある人はここで見えた、、などの噂を聞くことはありました。
(怖かったが私は見えませんでした)
注射は慣れるか
私は徐々に慣れました。
これに関しては、場数を積んでいくしかないと個人的には思います。
私が1年目の時の4年目の先輩たちは、「そんな所に血管ある!?」と思うところからもどんどんルートを取っていました。
そんな先輩方もみんな苦手だったが、やっていくうちに慣れたとのこと。
実際私も数をこなしていくうちに慣れていったので、まずはとにかくチャレンジしていくことが大切です!



逃げながら1年を過ごしていくと、あっという間に次の新人が入ってきてどんどんプレッシャーを感じる+そういった手技をさせてもらえる機会が減るので、早いうちにやる事をおすすめします!
ぶっちゃけ何からやるべき?
個人的には、【バイタルサインを覚える事】と、【物の位置を覚える事】だと思います。
1年目のうちはまずバイタル測定から始まっていくと思うのですが、「この値どう?正常?」と聞かれる事は多々ありました。
患者様のアセスメントにおいてもバイタルサインは最も基本的ですがとても重要なので、しっかり正常値を理解しておくべきです。
また、新人看護師はできる事が限られてきます。
そんな中できる事は「足で稼ぐこと」なので、なるべく物の位置は早い段階で覚えるにこした事はありません。
さらにもう一歩踏み込めば、処置に使う物品の準備もできるようになると最高です!



先輩から「採血の準備お願い」「Aラインの固定しておいて」と言われる事は多々あります。
院内マニュアルなどを確認して、必要な物品を事前に準備しておけるようになりましょう!
まとめ:上手に看護師1年目を乗り越えていこう!


いかがでしたでしょうか。
最初は慣れずにしんどい毎日かもしれませんが、できる事が徐々に増えていくとだんだん楽しくなっていくと思いますし、実際私もそうでした。
土日や休みの日はしっかりリフレッシュしつつ、成長していけるように頑張っていきましょう!
そんな皆様の力にこの記事が少しでもなれたら幸いです。
それではまた次の記事でお会いしましょう。
ここまで読んで頂きありがとうございました!